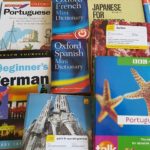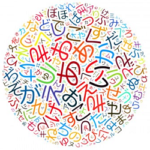キャリア国際機関のサイトを立ち上げ、国際機関キャリア支援サービスを始めて早二年半あまり。今年の主な活動と成果を振り返って見たい。
今年もほぼ2週間おきに、国際機関のキャリア開発に役立ちそうな記事をアップロードしてきた。掲載された記事は25件あまり。2017年にキャリアアドバイス、コーチング、応募書類添削、模擬面接等のサービスを利用した者は約70人。報告のあった範囲では、JPO試験を経ての者も含め、国際機関に採用されたものが7名とうれしい結果に結びついている。
筆記試験や面接までたどり着くも、無念の結果に終わる人がいる一方、JPOやYPP等の狭き門をくぐり試験に受かりながらも、赴任を迷う者もおり、キャリアとは人それぞれだなと強く感じた一年でもあった。
今年はレクチャーの機会にも恵まれた。外務省主催の応募書類書き方セミナーを東京で2度行ったほか、日本の大学向け講義が二度、某アメリカ大学のスイスキャンパス でもキャリア 開発セミナーを実行した。また日本の 大学院生及びジュネーブ国際機関訪問ツアーの学生たちに個別キャリアカウンセリングをする機会に恵まれ、若さの可能性を感じさせてもらった。
外務省人事センター等の努力のおかげで、国際機関就職関係の情報は充実している。しかし、個別のプロフィールやキャリアのニーズに合った 機関や空席を捜し、応募書類を作るための支援 は稀である。とくに地方の社会人や海外在住者は孤立しがち。アドバイスや適切な情報のないまま、プロフィールの合致していないポストに 応募を繰り返し、あきらめてしまうケースも多いと想像できる。
国際機関就職希望者のみならず現職員からもアドバイスやコーチングの依頼はあり、この分野でもキャリアサポートの強化は必要だろう。とくにJPOはコーチやメンターが早い時点からついていれば、 正式職員になれる可能性が高くなると思う。
なるべくたくさんの人に役立ちたいという思いから、キャリア国際機関のサービス料金は比較的低く設定してある。応募の成功、不成功にかかわらずアドバイスや面接、書類添削後の結果を知らせてもらえると、とてもやりがいがある。