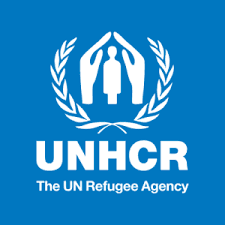近年は皆AIを使用して応募書類を書くので、英語ライティング力で差は付きにくい。だが同じような履歴でも採用側にアピールする履歴書とそうでないものがある。その差はどこから生まれるのか。
まず経験の記述量と描き方。国際機関がスクリーニングにかける時間は一分程度とされる。全ての職務を長々と詳細に記した履歴書は、読み手に負担を与え、場合によっては要点をまとめる能力に欠けると判断されることもある。
したがって、簡潔にまとめつつ、応募ポストとの適合性が一目で分かる構成を心がけたい。空席広告をコピーするのではなく、同じ様な表現や語彙を履歴書の目につきやすい部分に散りばめれば効果的。またアクション動詞で文を始めると、ダイナミックな印象を与える。
業績をいれる場合は達成した成果やインパクトを数字や変化で具体的に示す。履歴、業績ともポストとの関連性が高い事項をなるべく上位に配置すると注意を引きやすい。
文章スタイルとしては、否定表現より肯定表現、受動態より能動態を選ぶと読みやすく、語数も減らせる。AIの文は回りくどいものが多いので、動詞を吟味しlyで終わる副詞 (例completely, successfully)や場つなぎ言葉、無駄な表現 (例just, that, really, in order to, several, various, certain)をカットすると洗練される。
このように職歴を効果的に履歴書に反映できているか否かは、書類選考に決定的影響を与える。せっかくの履歴を100パーセント生かした書類で、最初のスクリーニングを突破したいものだ。