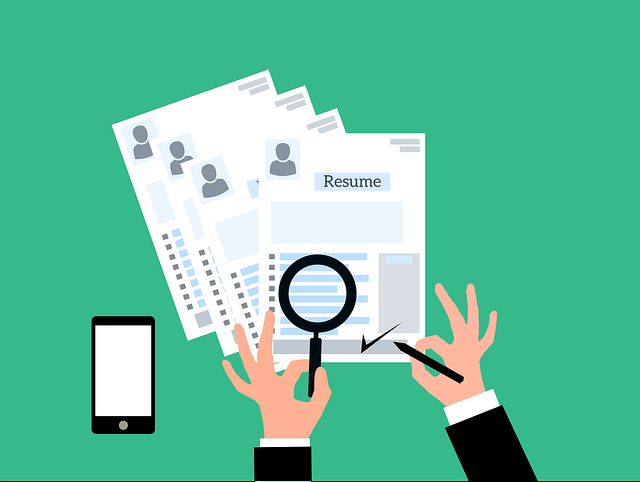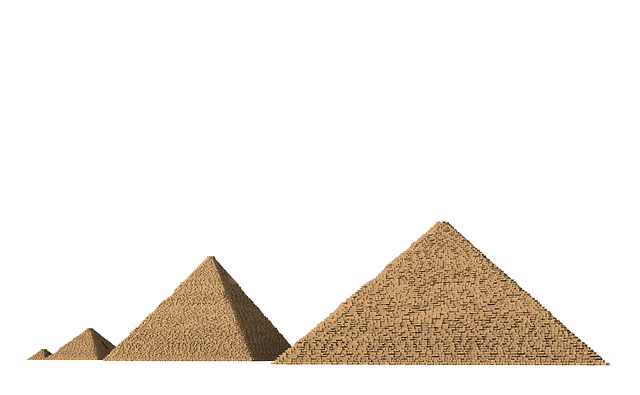国際機関に何度応募しても筆記試験や面接まで行き着けない、という経験はないだろうか。その場合もう一度空席広告を念入りに読み、自分のプロフィールと空席のマッチを確かめたい。空席広告の分析は応募成功に向けての重要な第一歩だ。
採用担当時代、空席広告を読んだとは思えない応募者の多さに驚いたもの。教育、経験年数、言語 Education, Work Experience, Languagesという3基本要素さえ満たしていない書類が大半だった。
国連の書類選考ではWork Experienceに記してある資格や特殊な経験が問われる。またdesirable, advantage, asset, などと書かれた部分も対象となる。特に外部からの応募者は、これらの条件もクリアしていないと次の採用プロセスまで進むのは難しい。
職務の記述は丁寧に読み、内容、責任の範囲やレベルをしっかり把握。自分の経験と職務内容が重なっている部分は、応募書類で強調する。面接でも具体例としてアピールできる。
空席広告の職種、部署、グレード、勤務地、契約、応募対象者等にも注目。ポストによっては内部職員のみ、ロスター登録者用などの応募者限定がある。また短期契約の場合、更新の可能性が示されているもの以外は、その期間限りと理解して応募する。国連システム以外の機関では給与やグレード体系が違うところも多いので、事前に情報収集をしておく。
勤務地も大切な要素だ。例えば地域事務所がフランス語圏にあると、言語の知識なしで応募しても競争力は弱いだろう。安全性が低く扶養家族が現地で生活することを認められていないnon family duty stationも空席には明示してある。
一般的でどのポストにも共通するコンペタンシー(例、communication, teamworkなど)は、どちみち面接で評価されるのであえて応募書類で強調する必要はない。
他方、国連の空席広告のPROFESSIONALISMの欄に記されているようなポストに求められる特有の知識、スキル、行動は、応募書類で強調。他の国際機関だとtechnical competencies (skills), job-related competencies, functional competencies など表現は様々だが、対象ポストに必要な独自の能力。例えば人権に関するデータの分析能力とか、Amazon Web Servicesの知識など。
このように空席広告には様々な情報が含まれている。自己のプロフィールとキャリアプランに合致したポストか、充分読み込み理解してから応募したいものだ。